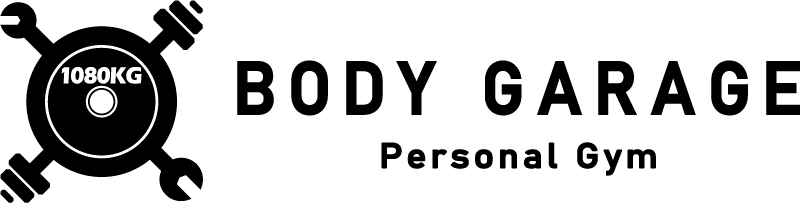いつもありがとうございます🙇
富山県高岡市にあるパーソナルジム
BODY GARAGEの石築(いしずき)です😊
今日も隙間時間に投稿失礼します😌📱
今日はタイトルの通り
疲労回復に関する事で
出したらきりがない…という面では
糖質、脂質、タンパク質を
自然な物から、色とりどり口に入れる事が
一番の健康と、疲労回復に繋がるんですが……
↑という話しはここでは置いといて。。。🤭笑
今回は10個掲載します‼️
写真はイメージ画を作成したので、もしかしたら
イメージ違いな物もあるかもです。。。
あくまでもイメージで…という風にご覧下さい。
【タートチェリー】
🍒 疲労回復の主なポイント
• 🏃♀️ 筋肉痛・筋損傷の軽減
• チェリーに含まれるアントシアニン(ポリフェノールの一種)には、抗炎症作用や抗酸化作用があることが示されています。
• 激しい運動後の筋肉の炎症や損傷を抑え、筋肉痛(遅発性筋肉痛)を軽減する可能性が研究で示唆されています。
• ⏱️ 筋力の回復促進
• マラソンランナーなどの研究で、チェリージュースを継続的に摂取することで、運動後の筋力の回復が早まったという報告があります。
• 😴 睡眠の質の改善
• チェリーは、天然のメラトニンを多く含んでいると言われています。メラトニンは睡眠リズムを調整するホルモンで、質の良い睡眠は疲労回復に不可欠です。

【オメガ3】
🐟 オメガ3脂肪酸と疲労回復の主なメカニズム
• 🛡️ 強力な抗炎症作用
• 激しい運動をすると、筋肉に微細な損傷が起き、炎症反応(筋肉痛や疲労感の原因の一つ)が生じます。
• オメガ3脂肪酸(特にEPA/DHA)は、この運動後の炎症を抑える働き(抗炎症作用)を持ち、炎症を解消する特殊な物質(レゾルビンなど)に変換されます。
• これにより、筋肉痛(DOMS)の軽減や筋肉の損傷からの回復を早める可能性が示されています。
• 💪 筋力・機能の回復促進
• 炎症を抑えることで、運動によって一時的に低下した筋力や関節可動域の回復を早める効果が期待できます。
• 🩸 血流の改善
• オメガ3脂肪酸は、血液をサラサラにする効果があるため、血流を改善します。
• 血流が良くなることで、損傷した筋肉に酸素や栄養素が効率よく運搬され、同時に疲労物質である老廃物の除去が促進され、回復をサポートします。
• ❤️🩹 心拍数の回復
• 運動後の心拍数が正常レベルに戻る時間(心拍数回復)が早くなるという研究結果もあり、心血管機能の回復にも寄与する可能性が示唆されています。

【コエンザイムQ10】
🧬 コエンザイムQ10と疲労回復のメカニズム
コエンザイムQ10は、私たち人間を含むほとんどの生物の細胞内に存在する補酵素です。特に、以下の2つの働きが疲労回復に関わります。
1. ⚡️ エネルギー産生をサポート (ATP合成)
• CoQ10は、細胞内の発電所であるミトコンドリアに多く存在し、栄養素から活動に必要なエネルギー源である**ATP(アデノシン三リン酸)**を作り出す過程で重要な役割を果たします。
• 体内のCoQ10が不足すると、エネルギーを十分に生み出せなくなり、疲れやすくなる原因の一つと考えられています。
2. 🛡️ 強力な抗酸化作用
• エネルギー産生の過程や激しい運動、ストレスなどによって、体内で活性酸素が発生し、細胞にダメージを与えます(酸化ストレス)。これが疲労感や老化の原因の一つです。
• CoQ10(特に還元型)は、この活性酸素を消去する抗酸化物質としても働き、細胞のダメージを防ぎ、回復をサポートします。

【カルニチン】
🥩 L-カルニチンと疲労回復のメカニズム
L-カルニチンの主な役割は、体内で最も大きなエネルギー源の一つである**「脂肪酸」を細胞内のエネルギー工場(ミトコンドリア)へ運び込む**ことです。
1. 🔥 脂肪をエネルギーに変換
• L-カルニチンは、特に長鎖脂肪酸をミトコンドリアの膜を越えて内部に輸送する**「運び屋」**として機能します。
• これにより、脂肪酸が効率よく燃焼(β酸化)され、エネルギー(ATP)として使われます。
• 疲労回復にはエネルギーが必要ですが、L-カルニチンがこのエネルギー供給をスムーズにすることで、疲労感やだるさを和らげる効果が期待されます。
2. 💪 運動後の回復サポート
• 激しい運動後、L-カルニチンを摂取することで、筋肉疲労の軽減や回復を早める効果が期待されています。
• 乳酸の蓄積を減らす作用や、血流や酸素供給を改善する作用が、この回復を助けると考えられています。
3. 🧠 精神的・肉体的疲労の軽減
• L-カルニチンは、肉体的・精神的な疲労感の感じやすさを減少させるというデータも出ており、幅広い疲労の軽減に寄与する可能性があります。

【クルクミン】
🟡 クルクミンと疲労回復の主なメカニズム
• 🛡️ 運動による炎症・損傷の軽減
• 激しい運動は筋肉に微細な損傷と炎症を引き起こし、これが**筋肉痛(遅発性筋肉痛、DOMS)**や疲労感の原因となります。
• クルクミンは、炎症を引き起こす物質(サイトカインなど)の働きを抑える抗炎症作用により、筋肉の損傷や痛みを軽減し、早期回復をサポートする効果が研究で示されています。
• ✨ 酸化ストレスの抑制
• 運動によって増える**活性酸素(酸化ストレス)**は、細胞にダメージを与え、疲労を増悪させます。
• クルクミンは、この活性酸素を消去する抗酸化作用を持つだけでなく、体内の重要な抗酸化物質(グルタチオンなど)の合成を間接的に高める働きも示唆されており、細胞の回復を促進します。
• 🏃♀️ 筋肉機能の改善
• 筋肉痛や炎症が軽減されることで、運動後の筋肉の可動域や機能の低下を抑え、パフォーマンスの早期回復に役立つとされています。

【ブルーベリー】
🫐 ブルーベリーと疲労回復の主なメカニズム
1. 🛡️ 強力な抗酸化作用と抗炎症作用
• ブルーベリーに含まれるアントシアニンは非常に強力な抗酸化物質です。
• 激しい運動によって発生する酸化ストレスや、それに伴う炎症を軽減する働きが研究で示されています。
• この作用により、運動後の筋肉疲労や筋肉の損傷が抑えられ、回復が早まる効果が期待されます。
• 実際に、運動の前後にブルーベリーのスムージーを摂取したグループで、筋肉の回復が促進されたという研究報告があります。
2. 👀 目の疲労(眼精疲労)の回復
• ブルーベリーが古くから「目に良い」と言われるのは、アントシアニンが目の網膜にあるロドプシンという物質の再合成を助ける働きがあるためです。
• 長時間のPC作業やスマホ使用による目の疲れ(眼精疲労)は、全身の疲労感にもつながります。アントシアニンは、目の調節機能の改善や血流促進を通じて、この目の疲労を和らげるのに役立ちます。
※目が良くなるわけではない‼️⚠️
3. ⚡️ エネルギー供給のサポート
• ブルーベリーには炭水化物も含まれており、これがエネルギー源として機能します。
• **低GI(グリセミックインデックス)**の食べ物であるため、血糖値の急激な上昇を避け、持続的なエネルギー供給が可能となり、運動中の持久力維持や、それに続く疲労の軽減に貢献します。

【BCAA】
💪 BCAAが疲労回復を促進するメカニズム
BCAAが疲労を軽減する作用は、主に「筋肉」と「脳」の2つの側面から説明されます。
1. 筋肉疲労・筋損傷の軽減(末梢性疲労)
• エネルギー源としての利用:
• BCAAは、他のアミノ酸と異なり、肝臓を経由せずに直接筋肉内で分解され、エネルギー源として利用されます。
• 特に激しい運動や長時間運動により、筋肉内の主要なエネルギー源であるグリコーゲンが枯渇しそうになると、BCAAが代わりにエネルギーとして消費されます。これにより、筋肉そのものが分解されてエネルギーに使われるのを防ぎ、筋損傷を軽減します。
• 筋肉の修復・合成促進:
• BCAAを構成するロイシンは、筋肉の合成を促すシグナル(mTOR経路)のスイッチを入れる働きがあり、運動で損傷した筋肉の修復(超回復)を早め、筋肉痛などのダメージを最小限に抑えます。
• 筋肉損傷の指標である**クレアチンキナーゼ(CK)**の上昇を抑制する効果が多くの研究で報告されています。
2. 脳疲労の抑制(中枢性疲労)
• トリプトファンの競合的抑制:
• 運動が長時間に及ぶと、血液中のトリプトファンというアミノ酸が脳内に入りやすくなります。トリプトファンは脳内でセロトニンという神経伝達物質に変わり、このセロトニンが増加すると「疲労感」として感じられる(中枢性疲労)と考えられています。
• BCAAはトリプトファンと同じ輸送体(運び屋)を使って脳に入るため、事前にBCAAを摂取しておくと、トリプトファンが脳に入るのを邪魔(競合的抑制)し、セロトニン過剰による精神的な疲労や集中力の低下を防ぐ効果が期待されます。

【HMB】
✨ HMBが疲労回復をサポートする主なメカニズム
HMBの主な働きは、疲労の主要因である「筋肉のダメージ」に直接アプローチし、その回復を早めることです。
1. 🛡️ 筋肉の分解を抑制(抗カタボリック作用)
• 激しいトレーニングを行うと、筋肉はダメージを受け、分解(カタボリズム)が始まります。
• HMBは、この筋肉の分解を抑える働き(抗カタボリック作用)が非常に強く、運動による筋損傷の進行を防ぐことで、結果的に筋肉痛や疲労感を軽減し、回復を早めます。
2. 💪 筋肉の合成を促進(アナボリック作用)
• HMBは、筋肉の合成を促すシグナル経路(mTOR経路)を活性化させ、筋タンパク質の合成を促進します。
• 損傷した筋繊維の修復プロセスをスムーズにし、筋力の回復を早めることに貢献します。
3. 😴 睡眠中の回復サポート
• 筋肉の修復は睡眠中に最も活発になります。HMBを就寝前に摂取することで、寝ている間の筋肉の分解を抑え、回復活動をサポートし、翌日の疲労や筋肉痛の持ち越しを防ぐ効果が期待されます。

【ビタミンD】
☀️ ビタミンDと疲労回復の主なメカニズム
1. 💪 筋力の維持と回復のサポート
• ビタミンDの受容体(センサー)は、骨格筋細胞にも存在しています。ビタミンDは、この受容体を介して筋タンパク質の合成や筋細胞の成長を調節し、筋力や運動機能の維持に不可欠です。
• ビタミンDが不足すると、筋力低下や筋肉の機能不全を引き起こし、これが全身の疲労感や回復の遅れにつながると考えられています。
• ビタミンDの補給によって、運動後の筋力回復が改善される可能性を示唆する研究もあります。
2. 🛡️ 免疫機能の調整と疲労軽減
• ビタミンDは、免疫細胞の働きを調整し、感染症への抵抗力を高めます。
• 風邪やインフルエンザなどによる体調不良は、大きな疲労の原因となりますが、ビタミンDが免疫機能を適切に保つことで、体調不良による疲労を予防する助けとなります。
3. 🧠 慢性的な疲労感の軽減
• 特に慢性的な疲労や説明のつかない倦怠感を訴える人において、ビタミンDの血中濃度が低い傾向があることが複数の研究で示されています。
• ビタミンDを補給することで、これらの人々の疲労感や倦怠感が改善したという報告もあります。

【クレアチン】
⚡️ クレアチンが疲労回復をサポートするメカニズム
クレアチンの主な役割は、細胞、特に筋肉における即時的なエネルギー源(ATP)の再合成を助けることです。
1. 🔋 ATPの再合成促進(エネルギー供給)
• 筋肉が高強度で短時間の運動を行う際、主要なエネルギー源は**ATP(アデノシン三リン酸)**です。このATPはすぐに消費され、**ADP(アデノシン二リン酸)**に変わります。
• クレアチンは、クレアチンリン酸として筋肉に貯蔵されており、ADPにリン酸基を提供することで、ATPを急速に再合成します。
• これにより、運動中にエネルギー切れによるパフォーマンスの低下や疲労の蓄積を防ぎ、結果として運動後の回復をスムーズにします。
2. 💪 筋力・持久力の維持
• クレアチンを摂取し筋肉内の貯蔵量を増やすことで、運動中の筋力やパワーの出力が維持され、疲労による急激なパフォーマンス低下が抑えられます。
• これにより、運動の質が維持され、トレーニング効果の最大化と、それに伴う全身の疲労軽減につながります。
3. 🩸 筋細胞の保護と炎症の軽減
• 一部の研究では、クレアチン摂取が筋細胞の損傷マーカー(クレアチンキナーゼなど)の上昇を抑制する、つまり筋肉の分解を抑える作用が示唆されています。
• これは、運動後の炎症や筋肉痛の軽減につながり、早期の疲労回復を助ける可能性があります。

とりあえず…
肉、野菜、魚、フルーツ
色々カラフルに食べると良い………ザックリな
調べた結果をまとめるとそんな感じですかね🤭笑
食材からとるには…という場合は
そこで有効活用するのがサプリメント(⚠️サプリメントの成分で記載していた物も有り)
私はどれか一つしかサプリメントがとれない‼️
となると
【マルチビタミン】一択
ですね‼️😊
さて、たまーーーーにする
まともな投稿でした🤣